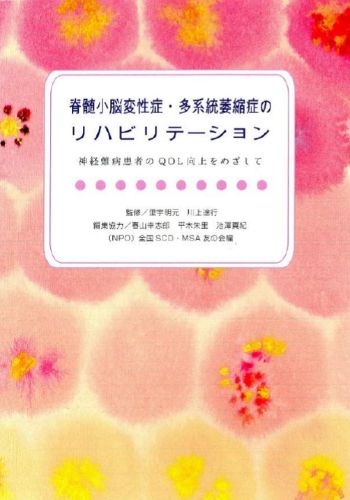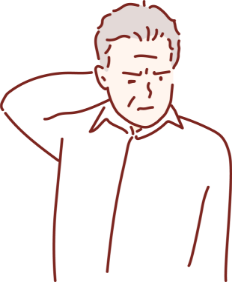病気の進行・予後
病気の症状は、軽症の方から医療ケアを必要とする方までさまざまです。病気が進行すると身体機能やコミュニケーション能力が障害されます。一般的な余命や病気の進行具合について医師から告げられる場合もありますが、病気の進行具合は患者さん一人ひとり異なります。同じ病型であっても、病気の予後が同じとは限りません。
病気と付き合っていくには、対症療法とリハビリを上手に組み合わせて、QOL(生活の質)を保ちながら療養生活を送ることが大切です。
治療法・治療薬について
それぞれの症状を和らげるための対症療法を中心に治療を行います。 SCD・MSAの薬剤による治療は、主に運動失調症状の進行を遅らせる、あるいは現状維持の手助けをする目的で、できるだけ早い段階から開始することがよいと言われています。
症状ごとに用いられる治療薬や療法
各症状に対して用いられる治療薬や対症療法を紹介します。
お薬は合う、合わないもあります。服用については主治医とよく相談しましょう。
漢方薬も保険適用薬として処方してもらえます。
- 市販薬よりも安いです。
小脳失調症状
小脳失調とは複数の筋肉をバランスよく協調させて動かすことができなくなる症状です。
甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(TRH)の効果が認められており、症状抑制効果があります。
先行開発薬のヒルトニン®は注射薬のため、週2〜3回ほどの点滴または筋肉注射が必要です。後発のセレジスト®は経口薬で1日に2回服用です。
セレジスト®とヒルトニン®は、脳内濃度の推移や内分泌学的作用の違いは若干ありますが、薬の作用などにおいては根本的に大きく異なる点はありません。
※ヒルトニン®(一般名:プロチレリン酒石酸塩水和物注射液):販売は武田薬品工業株式会社、製造販売は武田テバ薬品工業株式会社の医薬品です。
※セレジスト®(一般名:タルチレリン水和物):製造販売元は田辺三菱製薬株式会社の医薬品です。後発品のジェネリック薬品が複数あります。
パーキンソン症状
パーキンソン病に準じて、各種抗パーキンソン病治療薬を症状に合わせて用います。
起立性低血圧
末梢血管を収縮させ血圧を上昇させる薬剤と心臓の収縮力を高めて血圧を上昇させる薬剤を使用します。
排尿障害
原因に応じて膀胱や括約筋の収縮力を増加させる薬剤、膀胱や括約筋の過剰収縮を抑制する薬剤を使用します。しかし、SCDは膀胱や括約筋の収縮と拡張の両方が障害されていることも多く、薬物療法だけでは十分なコントロールができないこともあります。導尿(尿道口から膀胱内にカテーテルを挿入して尿を排出させるケア)や膀胱留置カテーテル(膀胱から直接尿を排出するために、尿道を通って、膀胱に長期間入れておくカテーテル)を使う場合もあります。
便秘
通常の緩下剤のほか、腸管運動改善薬や漢方薬などを使用します。
錐体路症状
大脳からの運動の命令を伝達する経路が障害され、運動麻痺などの随意運動に関する異常が生じます。 主に抗痙攣薬や筋弛緩薬が用いられます。症状をみながら少しずつ増減して使用する必要があります。
その他
けいれんを伴う場合には、抗てんかん薬を使用します。
注)治療薬の情報は、以下のサイトを参考にしています。
治験について
治験とは、薬事法に基づく医薬品・医療機器等の承認を得るために実施される臨床試験のことです。3 つの相(フェーズ)に分かれ、健康な人を対象として行われる第 1 相、少数の患者を対象に行われる第 2 相、多くの患者を対象に行われる第 3 相があります。医薬品や医療機器が承認された後に実施する製造販売後臨床試験は、第 4 相といいます。
治験の情報は、jRCT(Japan Registry of Clinical Trials 臨床研究等提出・公開システム ) :日本国内で実施されている(企業治験を含む)臨床研究全般の情報をみつけることができる公的なサイトで探すことができます。この情報をもとに、治験の参加についてご家族や主治医と相談してください。
「治験の探し方」のマニュアルは日本製薬工業協会(製薬協)のHPにあります。JRCT検索マニュアル
脊髄小脳変性症・多系統萎縮症に関する「募集中」の治験の具体的な検索方法は、次の通りです。
① jRCTの検索サイトにいく
② 画面上部にある「研究の進捗状況」で「募集前または募集中」を選ぶ
③ 画面中央にある「対象疾患名」で「脊髄小脳変性症」「or」「多系統萎縮症」を入力する
④ 画面下部にある「検索/Search」ボタンをおす

または「詳細検索へ」を押して、「臨床研究実施計画番号」にJRCT ID番号を指定して検索する。
詳細内容の見方は、JRCT検索マニュアルを参照してください。
海外で実施されている治験の探し方
主に米国で実施されている治験を見つけることができる公的なサイトは下記になります。
ClinicalTrials.gov(くりにかるとらいあるず どっと がぶ)
国際共同治験で日本が対象になっている治験も掲載されます。
検索方法やマニュアルは米国研究製薬工業協会(PhRMA)のHPにあります。
ClinicalTraialsのミカタ
ClinicalTraials検索マニュアル
リハビリについて
SCD・MSAは徐々に筋力が低下していくことがあり、リハビリテーションで筋力低下を防ぐことは重要です。日常的に歩く、起き上がるといった動作のリハビリや、体幹を鍛えてバランス感覚を養ったり、筋肉量を落とさないようにして身体の機能を保つようにしましょう。
最初にお読みください
早期にリハビリをすることで、症状が緩和されることが分かっています。
適切に行うことで症状を和らげ、身体の機能の低下を防ぎ、普通の社会生活を支障なく長く続けていくことが十分に可能となります。
大切なこと
筋肉量をなるべく保つことが重要です。筋肉があれば、寝たきりになる可能性が減少します。手に筋肉があれば、ふらついたとき物につかまることができ、転倒のリスクが減少します。また、足に一定の筋量が保たれれば体の安定性が高まります。そのほか、筋肉は骨格を支える役割も持ち、萎縮すると脱臼などの合併症を生じやすいことが知られています。
身体を動かさないままでいると、拘縮や廃用症候群と呼ばれるさまざまな障害を起こすケースがありますので注意しましょう。
在宅リハビリテーション
日常的にリハビリを行うことが大切です。できれば毎日、難しいようでしたら週に何回かリハビリを習慣づけましょう。自宅でできる一般的なリハビリテーションをご紹介します。実際に行う場合は、かかりつけの医師や専門家の指導・アドバイスを受けてください。
理学療法編(STEP1~3)
作業療法編(STEP1~3)
言語聴覚療法編(STEP1~3)
早口言葉で脳トレ&嚥下改善メニュー(動画とPDF)
集中リハビリテーションプログラム
脊髄小脳変性症において、集中的なリハビリテーションの有用性が報告されています。
一定期間バランス訓練、歩行訓練、上肢巧緻運動訓練、言語リハビリを集中的に行う事により、リハビリ期間内の日常生活動作(Activities of Daily Living:ADL) 改善のみならず、期間終了後も比較的長期間にわたって効果が持続することが立証されています。
リハビリテーション提供施設
当会が把握している、リハビリテーションを実施している病院は以下の通りです。
リハビリテーションを行うために他病院へ入院・外来を希望していることを、現在のかかりつけの主治医に相談した上で、一覧の相談先へ問合せ下さい。(主治医に相談がないと他病院でのリハビリテーションを受診できません)
| 所在地 | 施設名 | 集中リハビリ | 入院リハビリ | 外来リハビリ | 相談先 |
| 北海道 | 札幌西円山病院 | 有 | 可能 | 有 | 外来受付 |
| 宮城県 | 仙台西多賀病院 | 無 | 可能 | 無 | 地域連携室 |
| 群馬県 | 脳血管研究所美原記念病院 | 有 | 可能 | 有 | 地域連携室/ リハビリテーション部神経難病リハビリテーション課 |
| 埼玉県 | 埼玉県総合リハビリテーションセンター | 有 | 可能 | 無 | 医療相談室 |
| 東京都 | 国立精神・神経医療研究センター病院 | 有 | 可能 | 有 | 脳神経内科 |
| 神奈川県 | 昭和医科大学藤が丘病院 | 有 | 可能 | 無 |
脳神経内科 地域医療連携室 |
| 神奈川県 | 戸塚共立いずみ野病院 | 有 | 可能 | 無 |
脳神経内科 |
| 神奈川県 | 鶴巻温泉病院 | 有 | 可能 | 有 | 地域連携室 |
| 神奈川県 | 国立病院機構箱根病院 | 有 | 可能 | 無 |
地域医療連携室(医療相談室) |
| 静岡県 | 北斗わかば病院 | 無 | 可能 | 有 | 地域連携室 |
| 愛知県 | 愛知医科大学病院 | 無 | 可能 | 有 | 脳神経内科主治医 |
| 滋賀県 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 有 | 可能 | 無 | 脳神経内科 |
| 大阪府 | 森之宮病院 | 有 | 可能 | 無 | 医療相談室 |
| 島根県 | 松江医療センター | 有 | 可能 | 原則不可【要相談】 | 主治医より地域医療連携室へ |
| 福岡県 | 村上華林堂病院 | 有 | 可能 | 有 | 脳神経内科/地域連携室 |
| 熊本県 | くまもと南部広域病院 | 有 | 可能 | 有 | 脳神経内科 |